介護人材として外国人を受け入れる方法

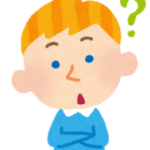
最近、外国人介護士が増えているとニュースでよく耳にします。なぜ外国人が増えているのでしょうか?また、どのようなビザで入国しているのでしょうか?

日本では、高齢者が急増しているにも関わらず、その高齢者をお世話できる現役世代が減っており、日本人だけでは必要な介護人材が足りないという深刻な問題を抱えています。
そのため、日本政府は外国から介護人材を積極的に受け入れる制度を整えています。受け入れ方法を以下の通り解説致します。
人材の受け入れ方法
①EPA(経済連携協定)
EPAは、日本とフィリピン・インドネシア・ベトナムの3か国との経済連携協定に基づく制度です。
自国で介護や看護を学んだ外国人を対象に、日本で実習を兼ねて働きながら国家資格(介護福祉士・看護師)の取得を目指します。
資格に合格すれば、その後も日本で介護福祉士や看護師として働くことが可能ですが、不合格の場合は帰国しなければなりません。
EPAは公的な枠組みのため、受け入れの調整機関は「国際厚生事業団(JICWELS)」に限定されている点が特徴です。
➁介護ビザ
「介護ビザ」は、介護人材の安定的な確保を目的に新設された在留資格です。
日本で介護福祉士の資格を取得することが条件となります。
多くの場合、留学生として介護系の学校に通い、資格を取得した後に介護ビザへ移行します。
また、特定技能ビザで働きながら資格を取得し、介護ビザへ変更するケースもあります。
介護ビザの大きな特徴は、家族の帯同が可能なことです。留学ビザや特定技能ビザでは家族帯同が認められていないため、資格取得後に介護ビザへ移行することで家族と一緒に日本で暮らすことができます。
➂技能実習(介護) →将来育成就労へ移行予定
技能実習制度は、日本の技術を外国人に習得してもらい、自国の発展に役立てることを目的とした制度です。
日本と協定を結んでいる国の送り出し機関を通じて受け入れが行われます。
介護分野での受け入れには、施設側にも介護福祉士の配置など一定の条件があります。
入国後、1年目・3年目の試験に合格すると在留期間が延長され、最長で5年間滞在可能です。
さらに、要件を満たせば「特定技能」へ移行して日本で引き続き働くことができ、介護福祉士資格を取得すれば「介護ビザ」への移行も可能です。
近年の方針として、技能実習制度は将来的に**「育成就労制度」へ発展的に解消・移行**する予定であるため、採用計画を立てる際にはこの点も意識する必要があります。
④特定技能(介護)
特定技能制度は、人手不足を補うために2019年に新設された制度です。
技能実習よりも即戦力として働ける人材を想定しています。
取得には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 特定技能評価試験(介護分野)に合格する
- 技能実習2号を良好に修了している
- 技能実習3号を修了している
在留期間は最長5年間で、日本の介護現場で就労することが可能です。
⑤ 国際結婚・配偶者ビザによる介護就労
外国人が日本人と結婚して「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザを持っている場合、就労制限はありません。そのため、介護の仕事に就くことも可能です。
このケースでは資格が必須ではありませんが、介護福祉士や介護職員初任者研修などの資格を取得することで、より専門的に働くことができます。
⑥ 永住者による介護就労
永住権持つ外国人も、就労制限がないため介護分野で働くことができます。
介護人材受け入れの課題と今後の方向性
日本語能力の壁
介護現場では利用者とのコミュニケーションが必須のため、日本語能力試験(JLPT)N3程度以上が求められることが多いです。
離職率の高さ
文化や働き方の違い、給与水準の問題から、定着率の低さが課題となっています。
新制度「育成就労」への移行
技能実習の廃止に伴い、介護分野でもより安定的に働ける制度が整備される見込みです。
受入れ企業・施設側の準備
外国人介護人材を受け入れるためには、以下のような対応が必要です。
- 就労ビザの取得・更新サポート
- 生活面での支援(住居、日常生活の案内など)
- 日本語教育や資格取得の支援
- 異文化理解や研修体制の整備
まとめ
外国人を雇用する際に最も重要なのは、適切な在留資格を選び、ルールに則って申請すること です。
在留資格ごとに活動範囲や要件が大きく異なるため、間違った手続きをすると不法就労につながるリスクがあります。
外国人雇用を検討している企業は、まずは「どの在留資格で採用できるのか」を確認することが第一歩です。
